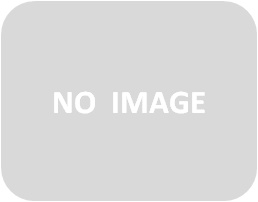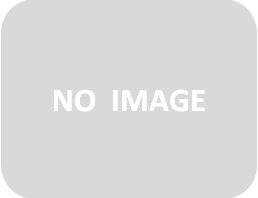秋分(しゅうぶん)
9/22~10/7頃
二十四節気が白露から秋分へと変わりました。
秋分は、太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜の長さがほぼ同じになる頃です。
太陽が極楽浄土があるという真西に沈み、先祖と通じ合える日とされていることから、秋分の日を中心とした一週間は、お墓参りをする習慣があります。


水始涸(みず はじめて かる):田畑の水を干し始める
末侯:10/3~
七十二候が秋分の末候に変わり、田んぼの水を抜き、稲穂の刈り入れを始める頃となりました。
井戸の水が枯れ始める頃との説もありますが、稲穂が実りの時を迎えるこの時季は、畦の水口を切って田を乾かし、稲刈りに備える時季でもあります。

蟄虫坏戸(ちっちゅう こを はいす):虫が土中に掘った穴をふさぐ
次侯:9/28~
七十二候が秋分の次候に変わり、寒さを覚えた虫たちが地中に姿を隠す頃となりました。
今回の候は、啓蟄の初候「蟄虫啓戸 (すごもりのむしとをひらく)」と対になっています。
夏が終わり、外で活動していた虫たちは寒さの到来を察知して、冬ごもりの支度を始めます。

雷乃収声(らい すなわち こえを おさむ):雷が鳴り響かなくなる
初侯:9/22~
七十二候が秋分の初候に変わり、春から夏にかけて鳴り響いた雷が収まる頃となりました。
今回の候は、春分の末候「雷乃発声 (かみなりすなわちこえをはっす)」と対になっています。
春分に鳴り始め、秋分に収まる雷、それは稲が育っていく時期と重なります。
二十四節気の「秋分」は、「春分」と同じく、昼と夜の長さがほぼ等しい日といわれていますが、実際は昼の方がわずかに長いのです。秋分の日を過ぎると、少しずつ夜の時間の方が長くなっていきます。秋は穀物や果物が収穫の時期を迎え、「実りの秋」といわれます。名前に「秋」のつく魚も旬を迎え、鰍(いなだ)、秋鮭(あきさけ)、秋鯖(あきさば)など、なかでも、秋刀魚(さんま)は、産卵前で脂がたっぷりと乗ってます。おいしいものがそろう季節に、「秋の味覚」「食欲の秋」を楽しみましょう。(2024.09.24)