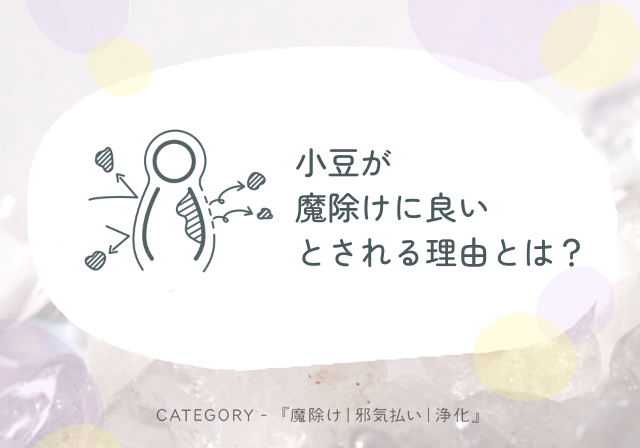お彼岸は春と秋、二度ある祈りの七日間
お彼岸は古来からある、日本独自の仏教行事です。故人を供養し、ご先祖さまに感謝を捧げるための「彼岸会」がお寺で催されます。この期間に墓参りに行き、花や線香を供え、手を合わせてお祈りします。お彼岸は春と秋の年2回あり、春は春分の日を、秋は秋分の日を、それぞれ「お彼岸の中日(なかび・ちゅうにち)」とよび、前後3日間ずつを含めた一週間がお彼岸の期間になります。春分の日、秋分の日は年により変わるため、お彼岸の期間もそれに伴います。お彼岸が始まる日を「彼岸の入り」、最終日を「彼岸明け」と呼びます。
豊かな自然に恵まれた中で暮らす日本人には、自然と調和することで、自然の流れを重んじる生き方が育まれました。農耕民族は太陽にその年の収穫を祈願する風土があり、春分の期間には種まきをし、秋分には豊作を願うという「日願(ひがん)」という考え方もあるといわれます。お彼岸はご先祖の供養だけではなく、植物を慈しみ、万物に感謝するという期間なのかもしれません。
仏教では仏さまの世界を「彼岸」と呼びます。三途の川を隔てたこちら側、私たちのいる現世の世界は「此岸(しがん)」と呼ばれます。春分の日、秋分の日は、太陽が真東から昇り、真西に沈むことから、ご先祖さまのいるとされる極楽浄土に通ずる、此岸から彼岸へ道が最も近くなると考えられ、供養の行事が定着していきました。
西の彼方にあるという極楽浄土
極楽浄土は、一切の苦しみのない安楽の世界のことです。「極楽」は、梵語(ぼんご・サンスクリット語)の「スカーパティー(sukhāvatī)」で「幸福のあるところ」と漢訳語されます。「浄土」を意味する梵語はありませんが、清浄な国土と表現される「仏国土」があるところと解釈されています。
浄土の意味するものには種類があり、西のはるか彼方には『阿弥陀如来の坐す西方極楽浄土』と、正反対の東には『薬師如来の坐す東方浄瑠璃浄土』の代表的な浄土世界があると説かれています。さらに、南方の補陀落という山には観音菩薩の浄土があるとも信じられています。仏教を信じる者は、仏さまの世界である浄土へ往生したい、仏さまの下で安楽に暮らしたいと強く願うことが信仰になっています。
日想観とは浄土教の仏事で、瞑想法の一種をいいます。太陽が沈む時、西の方向を向き、心を落ち着けて落日をじっと見つめると、やがて太陽が沈み、辺りは静寂と夕闇が訪れます。この瞬間、そこにまだ太陽が明瞭に見えるように観想することをいいます。目を閉じても開いていても、そこに太陽をありありと感じることが大切で、この修行が極楽浄土を見る修行になります。京都の清水寺では西門の夕景が名所になっています。
「厭離穢土欣求浄土」の教え
西方極楽浄土は浄土宗や浄土真宗の信仰する阿弥陀如来の世界であり、浄土宗のお寺はどこも阿弥陀如来が本尊となります。それに対し。天台宗や真言宗は観音菩薩や不動明王、大日如来など様々な本尊でお祀りしていますが、特に真言宗は大日如来を教主としています。
極楽の反対の言葉は「地獄」といい、浄土の反対は「穢土(えど)」として、『清浄な土地による世界が浄土、穢れた土による世界を穢土』と言われます。平安時代の終わりに末法思想が流行します。お釈迦さまの教えが絶えて、この世が天変地異や飢餓などで終わりを迎えようとしています。そんな穢れた世の中(土地)を離れて、清浄な世界(土地)であるあの世、つまり仏さまの世界へ生まれ変わりたいという祈りが「浄土往生思想」を生み出しました。
平安中期、天台宗の僧源信(げんしん)の著した『往生要集』には、穢れた世界であるからこの世界を厭い離れ、次生において清浄な仏の国土に生まれることを願い求め、『厭離穢土欣求浄土(おんりえどごんぐじょうど)』を説きました。この当時は「生まれ死に、死に生まれる」という輪廻の考えが常識の時代で、死んで阿弥陀さまの浄土に生まれ変わりたいと願う人が大勢いました。徳川家康にこの教えを諭したとされ、家康は以後、戦国の世を穢土とし、平和な世を浄土として「厭離穢土欣求浄土」を旗印と定めたことは有名です。
お彼岸の供養をする「彼岸会」のお供物
多くの地域では、お彼岸に法要を執り行い、お墓参りをするのが習わしですが、墓前や仏壇にお供物として「おはぎ・ぼたもち」を供えるのが定番になっています。あんこでもち米を包んだ和菓子なのですが、似たような食べ物であり、今では分けて呼ばれることも少なくなっています。しかし、もともとおはぎとぼたもちでは作る季節に違いがあり、別の呼び名になったのです。春には「ぼたもち」、秋には「おはぎ」としてお供えされています。なぜ名前が違うのでしょうか?諸説あるのです。
小豆の赤い色には魔除けの効果があると考えられたことから、身体を整え、神仏に手を合わせることで、無病息災を祈っていたともいわれています。小豆と貴重であった砂糖であんこを作り、これをもち米と合わせることで、ご先祖さまの心と自分たちの心を「合わせる」という意味もあるようです。また、贅沢といわれた小豆、砂糖、もち米を祀って、そのお下がりをおはぎ・ぼたもちとして頂いたという説もあります。
春のお彼岸には、牡丹の花のように大きく丸いこしあんの「ぼたもち」が、秋のお彼岸には萩の花のように小さく上品なつぶあんの「おはぎ」を供えます。花の名がその名の由来になっています。小豆の種まきが春の4月~6月で、収穫が秋の9月~11月であることから、秋のお彼岸時期は、収穫したばかりの柔らかい小豆でつぶあんの「おはぎ」を作り、春まで保存した小豆は硬い皮を取り除いたこしあんで「ぼたもち」を作っていました。現在は、小豆の品種改良や保存技術が発達したため、季節によるあんこの違いはないようです。
和菓子は四季や行事が大きく関わりす。季節や行事ごとに願いを込めて供えられた和菓子に加え、四季折々の美しさを意匠で表され、季節ごとに食べられる和菓子は楽しみですね。
夏の「夜船」、冬の「北窓」の遊び心
さて、春と秋で名の違う「おはぎ・ぼたもち」には、夏にも、冬にもそれぞれ名前を持っています。お餅は餅つきをして作るのですが、おはぎやぼたもちは、「もち」のようでも、もち米とお米を混ぜて炊き、すりこぎで半つぶしにして作るので、餅つきをせずに作ります。餅をつく「ペッタンペッタン」の音がしないので、いつついた「もち=つき知らず」なのか分からない。そういうことになります。
夏の「おはぎ・ぼたもち」は
つき知らず→「着き」知らず、となり、夜は船がいつ着いたのか分からないことから「夜船」と名がつきました。
冬の「おはぎ・ぼたもち」は
つき知らず→「月」知らず、となり、月の見えないのは、北の窓であることから「北窓」と名がつきました。
昔の人は、おはぎやぼたもちひとつをとっても季節毎の名前をつけるほど、自然や季節との結びついて、遊び心もありながら風情もあったんだと感心させられます。忘れてはいけない日本の心を思い出させてくれます。
春の「ぼたもち」、夏の「夜船」、秋の「おはぎ」、冬の「北窓」、身近なおはぎに隠されていました。
「暑さ寒さも彼岸まで」とは
「暑さ寒さも彼岸まで(あつささむさもひがんまで)」とは、『冬の寒さは春分の頃まで、夏の暑さは秋分の(前後)頃までには和らぎ、凌ぎやすくなる』という意味の慣用句です。お彼岸の時期を境として、季節が移り変わっていくことを表したものです。「暑い!」と、汗びっしょりになっていた夏も秋分の日を中日としたお彼岸でひと区切り、「寒~い!」と、ブルブル震えていた日々も、春分の日を中日としたお彼岸で春のぬくもりを感じられるようになる、そんな感覚があるのですね。お彼岸は、ご先祖の供養や豊作を祈る期間というだけでなく、季節の移り変わりを感じさせてくれる大切な習慣といえるのです。
また、本来涼しくなる、または暖かくなる時期なのに、まだ暑かったり寒かったりする時に使われる慣用句でもありますが、この意味が転じて、「『暑さ寒さも彼岸まで』なのだから、もう少し我慢しよう」のように、「辛いことも、いずれ時期が来れば去っていく」という意味の諺(ことわざ)として、「今はつらくても時が経てばいずれ去っていく」という意味で使われることもあります。同様に、「暑さ忘れて陰忘る(暑いときは物陰に入って涼んでいたのに、涼しくなるとすぐに日陰のありがたさなど忘れてしまう)」「喉元過ぎれば熱さを忘れる(煩悶するほどの苦痛、苦労、激痛も、それが過ぎてしまえばその痛みや苦しみをすっかり忘れてしまう)」も、同じ意味として使われています。四季折々の言葉でさまざまなに表現される言葉で季節を感じるのも日本ならではですね。