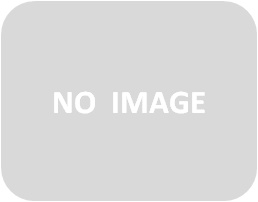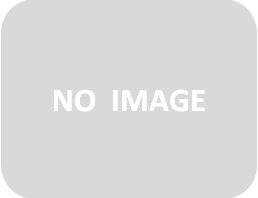今日の趣き -blog-
本ページはプロモーションが含まれています。
目次
1.奈良公園から南大門への参道へ向かう
2.大仏殿には毘盧遮那大仏が祀られる
3.1300年、東大寺の苦難の歴史
4.伝統に守られた、二月堂の修二会
5.最古の法華堂(三月堂)、1000年の四月堂(三昧堂)
奈良公園のあちこちにいる鹿は、人慣れしていますが飼育されているわけではありません。奈良公園に生息する鹿は国の天然記念物に指定されている野生動物です。奈良時代末期(8世紀後半)に成立したとみられる最古の和歌集である万葉集には、実際に鹿がいたことが書かれ、春日大社に祀られている「武甕槌命(たけみかづちのかみ)」が白いシカに乗ってやってきたという伝説があります。
東大寺は「奈良の大仏さま」で知られる奈良時代創建の寺院で、全国の国分寺の中心として建立されました。聖武天皇が「生きとし生けるすべてのものが栄えるように」と願い、盧舎那仏(るしゃなぶつ)造立の詔を発し、 天平勝宝4年(752)に大仏さまは開眼されました。 大仏殿は世界最大級の木造建造物です。
1.奈良公園から南大門への参道へ向かう
東大寺参道の正面に立っているのが、東大寺が誇るわが国最大の山門「南大門」です。天平創建時の門は平安時代に大風で倒壊し、現在の門は鎌倉時代、東大寺を復興した重源上人が中国から持ち帰ったとされる大仏様(だいぶつよう)という建築様式で再建した壮大な二重門です。正治元年(1199)に上棟し、建仁3年(1203)に竣工しました。二重門とは、上層と下層の両方に屋根が付く二階建ての門のことです。普通は、上層よりも下層の屋根の方が大きいのですが、南大門は上下同じ大きさの屋根で、下層は天井がなく腰屋根構造となった入母屋造、五間三戸です。屋根裏まで達する21mの大円柱が18本も使用され、門の高さは基壇上25.46mもある、大仏殿にふさわしいわが国最大級の重層門です。
創建時の東大寺には、高さ100mもの東塔と西塔という七重塔が並び建ち、金堂(仏殿)、講堂、中門、南大門、回廊、鐘楼(鼓楼)、経蔵などの主要堂塔が配置されました。南大門にはその大伽藍を守る国宝の仁王像「木造金剛力士立像」が安置されています。門の内左右には、口を開いて立つ阿形像(あぎょうぞう)と、口を閉じて立つ吽形像(うんぎょうぞう)が「阿吽(あうん)」の象徴として並びます。わが国最大級の木彫像で、像高は8.4mもありますが、運慶や快慶ら20数名の仏師により、わずか69日間で作り上げられたといいます。
東大寺 中門(とうだいじ ちゅうもん)は、国宝「大仏殿」の手前にある入り母屋造りの楼門で、享保元年(1716)ごろの再建と伝わります。両脇からそれぞれ回廊が伸びています。門は普段閉ざされていますが、毎年元日の0時から8時には中門を通って大仏殿への「初詣」として入ることができます。
中門の左側の大仏殿入堂口から入り、大仏殿の正面中ほどに、国宝の八角灯篭が立っています。4m超の大きな、金銅製の八角灯篭は、度重なる兵火で焼失したものが多い東大寺にあって、創建当時のままの姿を残しています。透かし彫りや経文を彫りつけ、細かい細工がされ、大仏に献灯するために設置されたものです。



2.大仏殿には毘盧遮那大仏が祀られる



東大寺の金堂(本堂)である大仏殿は、大仏とともに国宝です。大きさは、幅57.5m、奥行50.5m、高さ49.1mです。奥行き、高さは創建時と同じ大きさですが、幅が三分の二になっています。中で安座するのは、高さおよそ15mを誇る盧舎那仏です。創建当時は金メッキが施されており、眩いばかりの光を輝かせていたといわれています。水銀と金を練り合わせたものを塗って、その後炭火で水銀を蒸発させて表面に金だけを残すという方法が使われました。金は400kg以上で、水銀は2.5tも使われており、陸奥をはじめとした、日本全国から大仏を造るために献上されました。
盧舎那仏もしくは毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ/ヴァイローチャナ)といわれる大仏の意味は、「知慧と慈悲の光明を遍く照し出されている仏」ということで、「偉大で、正しく、広大な仏の世界を、菩薩のさまざまな実践の華によって飾ること」を説いています。鳥の声、花の色、水の流れ、雲の姿すべてが生きとし生けるものを救おうとする仏の説法なのです。聖武天皇は信仰していた仏教の考えと、国を守ることを目的として寺を建設し、生きとし生けるものがともに栄えること願い「大仏造立の詔」を発して、宇宙(世界)そのものを表す絶対的な仏として大仏を造りました。
聖武天皇は、天平15年(743)に東大寺の大仏造営の勧進役に行基を起用しました。行基は百済系渡来人の子孫で、668年に河内国大鳥郡(現在の大阪府堺市)に生まれました。682年に出家し、法相宗などの教学を学んだとされています。和同3年(710)の平城遷都の頃から、弟子を率いて布教と貧民の救済や治水、架橋などの社会事業に取り組み、過酷な労働からの逃亡・流浪する民が行基の下に集まります。人々から行基菩薩と崇められるほどの支持を集めましたが、時の政府からは民衆を扇動する危険人物とされ、糾弾を受けても、その活動と名声は各地に広まりました。社会的信望を集めた行基は東大寺の大仏造営の勧進役に起用されました。天平17年(745)に朝廷から日本初となる大僧正の位を贈られ、大仏の完成を見ることなく、天平21年(749)に82歳で亡くなりました。
3.1300年、東大寺の苦難の歴史
奈良時代、人々は天然痘の流行や度重なる飢饉、政争に伴う政変や戦に疲弊していました。神亀6年(729)に、藤原氏の策略より左大臣長屋王が自尽させられる排斥事件が起き(長屋王の変)、政権を握った橘諸兄と対立して大宰府に左遷された藤原広嗣が、天平12年(740)に九州太宰府で兵を挙げて(藤原広嗣の乱)反乱を起こしました。このような災難の連続を憂えた聖武天皇が、大きな力で民衆を救いたいと願い、その大きな力をもつ廬舎那仏の建立を思い立たれました。天平15年(743)に詔(みことのり)を発し、天平勝宝4年(752)に開眼供養会(かいげんくようえ)が開かれました。実に、9年の歳月を費やして完成させました。
正倉院は、東大寺大仏殿の北北西にある、校倉造の大規模な正倉です。聖武天皇・光明皇后ゆかりの品をはじめ、天平文化を中心とした多数の美術工芸品を収蔵していた建物で、「古都奈良の文化財」の一部としてユネスコの世界遺産に登録されました。
大仏や大仏殿は、度重なる自然災害や戦火を潜り抜けて、今の姿があります。斉衡2年(855年)、地震で大仏の頭部が落ちます。また、平安時代の末、保元・平治の乱の後、平氏は寺院勢力と対立し、治承4年(1181)奈良の都を焼き払い、東大寺は、二月堂・法華堂(三月堂)・転害門・正倉院以外の主要な伽藍を失ってしまいました。その後、後白河法皇や武家の協力、支援で大仏が再建され、その後、大仏殿も再建されました。
東大寺大仏殿の戦い(とうだいじだいぶつでんのたたかい)は、将軍足利義輝を殺害した三好三人衆と松永久秀が主導権を巡って、永禄10年(1567)のおよそ半年間にわたり東大寺周辺での市街戦で、南大門で銃撃戦が繰り広げられました。その際に松永秀長が大仏殿に火をかけ、大仏殿は焼け落ちました。その後、仮堂で復興しましたが、大風で堂が倒壊、大仏の頭も落ち、雨ざらしの首なし状態が続きました。その後、100年以上の時を経て、徳川時代の宝永6年(1709)にようやく大仏殿と大仏が再建されます。これが現存する奈良の大仏です。



4.伝統に守られた、二月堂の修二会



奈良の都に春を告げる法要といえば「修二会」です。「二月堂」を創建して、天平勝宝4年(752)から伝えられてきた最も重要な行事です。修二会は、東大寺開山良弁僧正に師事して華厳を学んだ高弟の実忠(じっちゅう)が創始し、以来、令和7年(2025)には1274回を数えます。修二会のためだけに二月堂は造られました。
実忠は、木津川の南岸にそびえ、古くからの修験道場、信仰の笠置山で見た天界の菩薩たちの法要に感動し、人間界でも行いたいと願い、「天界の速い時間の流れに追いつくために走って法要を行う」と誓いました。実忠は「走り」を考案し、お堂の中を休みなく走って祈り、「達陀(だったん)という火の神と水の神に祈る火炎の舞う荒行」や、「五体投地(ごたいとうち)」という荒行も行わせました。
古代では、国家や万民のためになされる宗教行事であり、天災や疫病や反乱は国家の病気と考えられ、そうした病気を取り除いて、鎮護国家、天下泰安、風雨順時、五穀豊穣、万民快楽など、人々の幸福を願う行事とされました。東大寺の長い歴史にあって、二度までもその大伽藍の大半が失われてしまった時ですら、修二会だけは「不退の行法」として、1250有余年もの間一度も絶えることなく、連綿と今日に至るまで引き継がれてきたのです。
現在では3月1日より2週間にわたって行われますが、もとは旧暦の2月1日から行われました。二月に修する法会という意味をこめて「修二会(しゅにえ)」と呼ばれるようになり、二月堂の名もこのことに由来しています。12日の深夜になると、「練行衆(れんぎょうしゅう)」と呼ばれる修二会のために選ばれた僧侶が二月堂に足を運び、清水をくんで観音様に捧げます。この儀式にちなみ、東大寺の修二会そのものが「お水取り」と呼ばれるようになりました。また、この行を勤める練行衆の道明かりとして、夜毎、大きな松明(たいまつ)に火がともされます。このため「修二会」は「お松明」とも呼ばれるようになりました。
5.最古の法華堂(三月堂)、1000年の四月堂(三昧堂)
法華堂(三月堂)は、東大寺最古の建造物です。堂内には合計10体(国宝、奈良時代)の仏像がところ狭しと立ち並んでいます。特に3mを超えるご本尊‧不空羂索観音菩薩立像(ふくうけんさくかんのんりゅうぞう)は煌びやかで、その宝冠には多数の宝玉が散りばめられています。これらの群像のかもし出す雰囲気は、観る人をしばし厳かな「ほとけたちの世界」に誘います。
堂々たる体軀で、悩める人々をどこまでも救いに赴こうとされている不空羂索観音像、髪を逆立て、忿怒(ふんぬ)の相もすさまじい金剛力士像、それぞれにほとけの世界を守ろうと多様な表情でたたずむ四天王像、それに東大寺創建以来今なお色あざやかに、金剛杵を振り上げ忿怒の相で仏敵より人々を守ろうとする秘仏執金剛神像(しゅこんごうじんぞう)など、天平彫刻の粋が集まっています。かつて、本尊の両脇にたたずんでいた(伝)日光・月光(にっこう・がっこう)両菩薩像や、吉祥天像(きちじょうてんぞう)、弁才天像(べざいてんぞう)は、耐震対策上、東大寺ミュージアムへ移されています。
東大寺ミュージアムでは「東大寺の歴史と美術」をテーマとして、常設展示および特集展示などを行っています。
常設展示ではミュージアムの本尊である千手観音菩薩像のほか、法華堂伝来の日光・月光菩薩像、奈良時代の誕生釈迦仏像や大仏開眼供養に用いられた伎楽面など、多くの寺宝をご覧いただけます。
四月堂(三味堂)は、かつて旧暦の4月に法華経に由来する法華三昧会が行なわれました。古くは普賢堂、普賢三昧堂とも呼ばれ、普賢菩薩が本尊だった時代もあり、堂内には小像ながら平安期の普賢菩薩騎象像を安置しています。法華経を信仰する者のところに、白い象に乗って現れる姿を表しています。
平安時代の治安元年(1021)に創建、あるいは治暦3年(1067)の説もあります。現在の建物は方三間の二重寄棟造で、化粧裏板の墨書から江戸中期、延宝9年(1681)の建立され、随所に鎌倉期に遡ると目される古材が用いられ、重要文化財に指定されています。堂内には十一面観音像や阿弥陀如来像(いずれも重要文化財)など、平安期の仏像も安置されています。