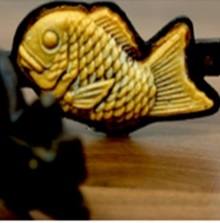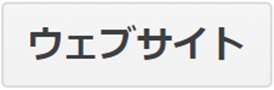餡子が入った、日本伝統の甘いお菓子
「あんこ」は漢字で「餡子」と書きます。あんこは小豆などを煮て、たっぷりの砂糖を加え、練り混ぜて甘いお菓子になります。小豆のあんが一般的ですが、他に白いんげん豆(白あん)や青えんどう豆(うぐいすあん)、枝豆(ずんだあん)などがあります。また、豆以外でも、かぼちゃや栗、さつまいもなどでも作られます。小豆の粒をつぶさないあんを「つぶあん」、 つぶし気味で皮を取り除かないあんを「つぶしあん」と呼び分け、やわらかく煮たアズキを裏ごしして皮を取り除き、練り上げたものが「こしあん」です。さらに、こしあんに大納言など大粒の小豆を蜜煮にしたものを混ぜ合わせ「小倉あん」を作ります。
「餡」は、中国の料理では食物に中に詰めて調理する詰め物のことで、現在の肉まんや餃子、シューマイのことでした。飛鳥時代に遣隋使により伝えられた当時は、饅頭に肉や野菜が材料の詰めもののことでした。その後、仏教の影響で肉食が避けられ、小豆を使った現在のあんこのようになりましたが、味付けは塩でした。安土桃山時代になって、甘い餡が作られ、江戸時代になって砂糖が使われはじめ、ようやく庶民も口にできるようになりました。そして、大福餅やきんつば、おはぎなどの商品が生まれました。
近代以降、庶民の楽しみである和菓子も多様な広がりがあり、西洋文化の移入によって食文化は大きく変わりました。新たな食材を使ってあんを作り、バター、チョコレート、生クリームやカスタードクリーム、ベリージャム、ナッツなどで試みられています。あんを使った和菓子も多く市場に現れ、昔からの、饅頭、餅、団子、大福、きんつばなど、また、あんぱん、あんドーナツに使われたり、お汁粉、ぜんざい、かき氷、アイスキャンデーにもなりました。中でも、あんこの和菓子、どら焼き、たい焼き、今川焼きは庶民の楽しみになっています。
どら焼き
どら焼きは、やわらかにふっくらとした円盤状のカステラ風の生地2枚に、小豆あんを挟んだ和菓子です。どら焼きの名前は、楽器の「銅鑼(どら)」に生地の形や色が似ているからだといわれます。昔からある粉物の菓子と同じく、材料は小麦粉、卵、砂糖を一定量の配合により生地が作られます。蜂蜜やみりんでやわらかさや風味を加えたり、独自の工夫を編み出すことで、全国の和菓子職人が多様などら焼きを作り上げました。

日本各地、いろいろなどら焼き
東京都千代田区神田東松下町49
福岡県うきは市吉井町1051−1
山梨県北杜市大泉町西井出8240-5060
たい焼き
たい焼きは、鯛の形の金属製焼き型に溶いた小麦粉を焼き、餡を包んだ、鯛の形をした和菓子です。江戸時代の今川焼から派生して作られたといいます。明治時代の『たべもの起源事典』によると、1909年創業の浪花家総本店の初代神戸清次郎が創作したとしています。 その経緯は、「今川焼きを始めたが一向に売れず,亀の形の亀焼きも失敗する. ところが,めでたいタイの姿にしたところ,(略)飛ぶように売れ、広まっていったという」と紹介しています。

日本各地、いろいろなたい焼き
東京都港区麻布十番1-8-14
神奈川県足柄上郡山北町中川921-83
東京都渋谷区恵比寿1丁目4−1 恵比寿アーバンハウス 107
今川焼き
今川焼は、小麦粉、卵、砂糖を水で溶き、鉄や銅製の丸く窪んだ金属製の焼き型へ流し入れ、餡を包み込みながら焼き上げた和菓子です。同じ原料で作られた菓子でも、形が違ったり、呼び名の違う様々なものが、全国各地で同様な食品が作られています。明治時代は庶民のおやつとして大流行し、森永製菓創業者の森永太一郎が「焼芋屋と今川焼がある限り銀座での西洋菓子の進出は困難」と言うほど、盛んに売られていたようです。

日本各地、いろいろな今川焼き
東京都世田谷区太子堂4丁目1−1
広島県尾道市東御所町3-8
山口県周南市銀座1-19